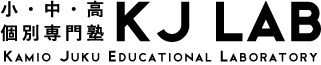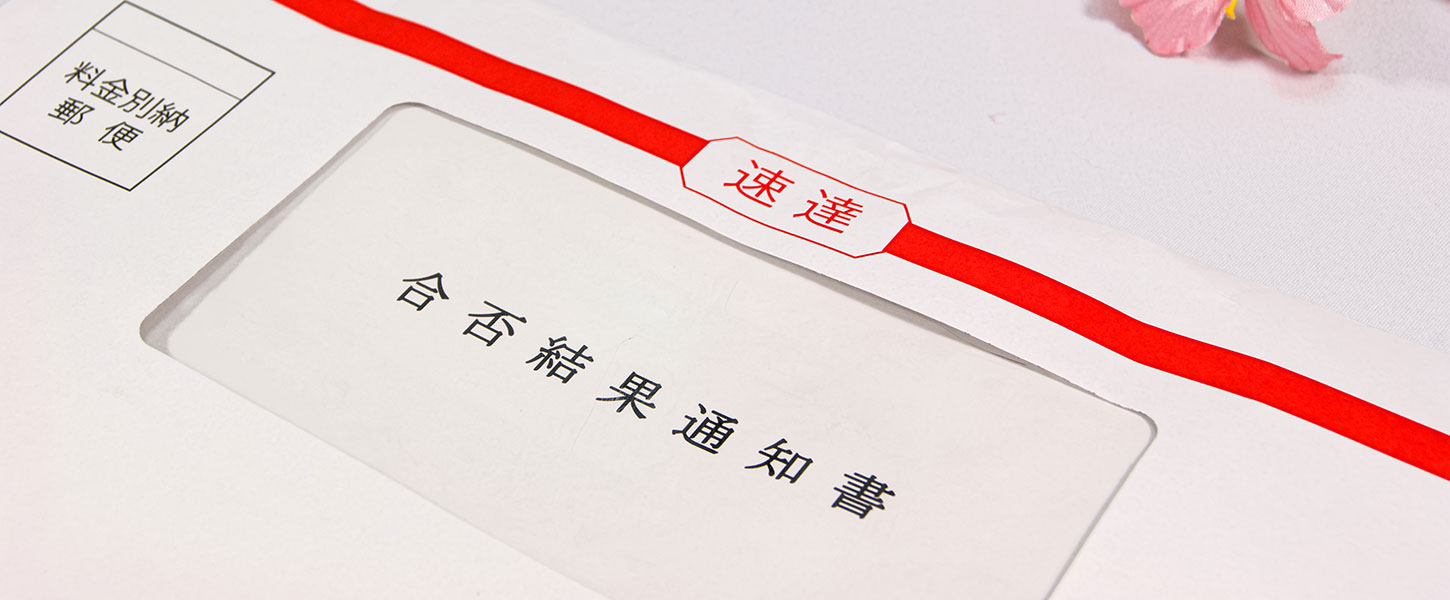10年くらい前の話だが、高校3年のI君が大学受験で小論文と面接の試験を受けることになった。指定校推薦だったので、高校の校内選考を通過した時点でほぼ合格といってよい状況である。
準備を重ねて本番。そして、合格発表の日。
ところが、I君は涙目で塾にやってきた。まさかの不合格だった。
この結果は高校の方でちょっとした騒ぎになって、大学側へ原因を問い合わせる事態になった。
ひとつ判明したことは、面接官の教授の「合格が決まったらどうするか?」の問いに、I君は「勉強とアルバイトをします」と答えてしまったことであった。
自分はどうせ合格するから、と油断していたのだろう。
たまたま厳しい面接官だったことも間違いない。「大学に何をしに来たのか」を明確に問うた教授だったのだ。
・・・I君はその後、他大学に進学して、現在は立派な社会人になっている。この経験はI君にとって人生の大きな肥やしとなっているはずだ。
◆
同様のエピソードは多い。
漫画家の水木しげるは戦前、美術学校に入りたかったが高等小学校卒で美術学校(現在の東京芸大)の受験資格がなかったので、経由地として大阪府立の園芸学校を受験することになった。
その年の園芸学校の入試は定員50名に対して受験者51名。不合格になるのが不思議なくらいの状況だったが、本番の面接で水木しげるは「卒業したら画家になりたい」と正直に言ってしまった。
結果、不合格。たった一人の落伍者が、水木しげるだったのである。
◆
これはどういう教訓かと言うと、
受験する学校のポリシーに沿って回答しなければならない、ということだ。
当塾だって入塾の段階で「〇〇塾もいいと思ったけど、とりあえずKJ LABに来てみた」となれば「それなら〇〇塾に行って下さい」となる。
あまり自分を繕ったり、明らかなお世辞を言うのも感心しないが、受験する学校のパンフレットを徹底的に読み込んで頭に入れ、その学校生活の中で100%全力投球できる自分像を面接で描くことが大切なのだ。
◆
当塾についての詳細な情報はこちらをご覧ください。