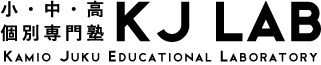安岡正篤先生の「現代活学講話選集」より。
「識」には3つある。一つは「知識」で、これは一番つまらん。雑識と言いますけれど、これはあまり値打ちがない。人間には単なる知識ではなく「見識」、価値判断が大切である。見識がなければ語るに足りん。ところが見識があっても、その人が臆病である、狡猾(こうかつ)である、軽薄であるというと、その見識も何の役にも立たん。いかなる抵抗があっても、いかなる困難に臨んでも、確信するところ、徹見するところを敢然として断行し得るような実行力・度胸を伴った知識・見識を「胆識」という。見識があっても胆識がない人はたくさんいる。しかし人間は、胆識があって初めて本当の知識人である。(P.23)
ちょっと語弊があるかもしれないが、「偏差値の高いバカ」は世の中に少なくないように思う。「偏差値の高いバカ」というのは、モノを覚えたり、やたらと知能は高いが心が伴っていない、心が幼い、心が発達していない人のことである。生まれつきスポーツの得意な人がいるように、偏差値が高いということについて、生来の素質として持ち合わせている人もいる。しかし、それは一つの「芸」に過ぎない。
学校説明会で今年は阪大に〇〇人合格しました!同志社大に〇〇人合格しました!というのは、「じゃあ結局全員阪大に行けばいいのか」「全員同志社に行けばいいのか」という皮肉も言える訳で、そういう合格者数至上主義のような価値観ばかりの学校になってしまうと、学校の存在意義そのものが頭打ちになってしまう。
「俺、それ知ってるよ」と口達者な「知識バカ」では全く意味が無く、モノを見抜く「見識」が必要。それを肝の据わった覚悟と共に日常生活における実行力につなげて「知識」の価値が光を放つ、と。
古人がいかに心術・識見、つまり「胆識」を磨いたかということである。現代の風習は論理と法令に馳せて、内省と修徳とに怠慢である。「治人あって、治法なし」(荀子:じゅんし)という名言があるが、いまは「治法あって、治人なし」の感がある。法律はいくら作ってみたって、その通り行われるものではない。しかし結局、やはり治人に待たねば治法にならない。(P.24)
例えば、「塾に音の出る時計を持ち込んではいけない」とルール化して規約に盛り込んだとする。でも、音の出る時計がなぜダメかというのは、時報の音が教室に響けば、時間本位ではなく内容本位で自分の勉強に取り組んでいる生徒にとって「あ、8時だ」「もう9時だ」と時間を意識させることになってしまい、場合によっては時間を気にすることも必要な時もあるが、時間を意識することが害になる時もある。そういった条文をいちいち規約に盛り込む必要があるか、という問題。
「ああ、迷惑になるな、この時計は塾に持っていかないようにしよう」
「ルールでダメだから持っていかない」のではなく、「他人の迷惑になるから持っていかない」と自分で気づく。前者が治法、後者が治人だ。
結局、人間が駄目ならばどれだけたくさんルールを設けてもキリがない訳で、だからこそ<治法>よりも<治人>の方が遥かに価値が高いと言っている。
君主は国家社会のための存在であるから、日頃の言行はすべて公の立場から発する言行でなければなりません。(P.32)
これは国に限らず、家庭でも、学校でも、部活動でも、リーダーは常に何を前提に考え、ことばを発するかという戒めを述べている。部長だったらクラブの発展と部員の成長のために言葉を発し、行動しなければならない。
どうにもならないような退廃的傾向の世になったときに、すぐにどうしよう、こうしようとしたって、できることじゃないので、無理にやろうと思うと、とんでもない副作用にかえって破れることがある。それよりは、種を残す、こういう傾向を救えるような種、人物・精神・道徳・信仰、そういったものを残す。そうすると、時が来たら、それが必ず育って自ずら世を救う。この時にあたっては、天下の俗流というか、時流・俗流というものに、毅然として動じないような人物・精神、そういう道義・信仰というものを大事にすることで、そうすれば、時が来れば必ず時代を、人心を救うことができる。これは確かにそうであります。(P.65)
「感染者数〇〇〇人、昨日は〇〇〇人、大変だー!」と、表面的な数字で右往左往するのではなくて、その数字の奥に流れている動向は何だろうかと、少なくとも塾通信の塾生向けお知らせに随時記載しているURLのリンク先を読んでおくだけで、それなりの見識を養うことの一助になっているはずだ。先ほどの「知識・見識・胆識」の三連動はまさにそれだが、本当に連日テレビばかり見ていたら馬鹿になると思う。テレビのニュースを見て動揺する時間があったら、ひとつ人生の足しになるような本でも一冊読んだ方がよほど人生にとって価値がある。
だいたい、人間はいくら才能や学問が優れていても、その人物相応の見識というものがなくては、天下国家の大事を片づけることはできないのではありませんか。その見識を進めるにはどうすればよいかというと、体験に根ざし叡智から発するところの学問よりほかありません。その場しのぎの間に合わせの学問ではなく、世界の先の先を見通すだけの見識がなくては、大事を成しとげることはできますまい。物事を鏡に映すように見通して、てきぱきと明快に判断することも見識があって初めてできるのだと思います。(P.100)
「勉強して何の意味があるの?」「計算は社会に出てからも使うし、英語はこれからの国際化のために…」といった問答は上っ面ばかりのつまらない話。勉強は勉強をすることそのものに意味がある。途中式をしっかり順序立てて書こう、ということも思考の整理だけでなく自分を律することに繋がる。公式を組み合わせて問題を解くことも、世の中の複雑な現象から要素を繋ぎ合わせて仕事を生んでいくような、そういった実社会で生きるための頭の体操であり作法であり、デモンストレーションになっている。
剣道はなぜ「剣の道」なのか。相手を叩いて、刺すだけだったら「剣」だ。その剣の動きを通して一つの人生の「道」を習得するから剣道であって、それは柔道でも華道でも茶道でも、どの手段でも極めれば一つの人間の境地に行きつくから「道」と名がついている。そういう意味で、勉強することも一つの「道」ということになる。
いくら本を読んで、知識を豊富に持っておっても一つも実際の役に立たんという学者がある。こういうのを迂儒(うじゅ)という。いろいろ知ってはいるが、意外に役に立たん、生きた解決にピタリとしないというのを迂と言う。だから儒者でも、物知りではあるけれども活きた学問にならんというのを迂儒という。
しからば、見識をどう養うか。それは、やはり人生の体験を積んで、人生の中にある深い理法、道というものがわからないと見識になってこない。余談になるが、私は珍しく親しい医者から懇請されて、専門の医者の集まりに出て、一夜、大変愉快な、有益な会談をしたことがある。そのときに、たまたま「人間とは何ぞや」という問題から、知識だの見識だのという問題も出た。話を聞いておった一人の医科大学の教授で、これは内科の大変な権威でありますが、しみじみと、
「このごろの医者は恐るべき堕落、あるいは危険をおかしておる。それは今日の医学技術が非常に発達をして、発達した結果、医道というものを失ってしまって、いわゆる医者としての機械的な知識や技術になってしまっているためだ。せっかく患者が来ても、彼らをまずそれぞれの専門に回して、呼吸がどうだ、心臓がどうだ、尿がどうだ、血圧がどうだとそれぞれ専門の係のところへ回して、データを採らせる。そうして、主治医は集めたデータで、この患者はここが悪いとか、何とか判断する。
これは患者という人間を診ておるんじゃないんです。患者という単なる肉体を分解・分析的に診ておるにすぎない。ところが、人体というものは、機械じゃない。機械的に診ることはできるが、人体そのものは機械じゃなくて生命である。生命体である。だから、端的に言うならば、血圧にしたって、あるいは脈拍にしたって、あるいは血液すべてがこれは物質ではなくて、生命体であるから、それぞれの患者で皆違う。同じ肉体の中でも打診してみると、その日その時によって、音が違う。
肝臓を叩いた音と、胃を叩いた音と、肺を叩いた音と、打診がすべて違う。病状によっても違っておる。人間の体を打診してみると、これは主治医が自ら多年の体験と英知とでそれを見分け聞き分けなきゃならん。それを何もわからない助手なんかに十把一からげに機械的に調べさせて、そんなデータを集めて患者を判断するなんて、これは患者抜きの、要するに人間不在の医療だ。今日の医学は医学と言えるかもしれないが、少なくとも医療とは言えん、人を医するとは言えない、医人じゃなく医物である。物を医しているのだ。
まず今日の医療の改革をやろうと思うと、医とは何ぞやと、結局それはもっと突き詰めると人間とは何ぞや、生命とは何ぞやということを教えて、それからその人を初めて診る道に入れるので、それはまったく物質化し機械化してしまって、人間不在、生命抜きの医学医療になっておるから、恐るべきことである。今日のような医学校がこれ以上増えたら、おそらく医者によって人間は殺されてしまうだろう」と、言うておりました。なんの道もそうであります。(P.102-104)
これは医学の例に限らず、教育でも美容でも料理でも、どのジャンルにも通用することだと思う。
どの道であっても、一つの経験を重ねてくると全てのものが「繋がっている」ことに気づく。剣道でも柔道でも茶道でも、極めると富士山の頂上のように一つの頂点に行きつく、上から見れば登山道は登り方次第で無数に広がっていることが理解できるが、ふもとから見れば頂上を目指すにも手前の断片の道をかき集めていくしかない。この断片をかき集めるだけで終わるのか、ひとつの頂上を悟るまでに至れるのか。
例えば、大学に行くと大学4年卒で「学士」、大学院の前期課程で「修士」、後期課程で「博士」という学位が得られるが、「博士」というのは「博」と書いて「ひろし」と読ませる名前があるように「博(ひろ)く学問を修めた者」という意味合いがある。
そして、自分にとって「これだ!」と突き進んだ特定のジャンルに絞って研究し、そこで論文にまとめて「博士」の学位を取得する。
工学部であれば、建築の中の材料を究めても、デザインを究めても、地震を究めても、工学博士になる。土木も機械も電気も同様に、工学博士になる。工学博士になると、建築や土木、機械や電気といった細かい分野を網羅する「工学」という富士山の頂上を得られるから、その「工学」の知見によって工学全般についてモノを語ることが出来る。
私が好きな、宮沢賢治の『稲作挿話』。
--これからの本統の勉強はねえ、テニスをしながら商売の先生から、義理で教はることでないんだ--
断片なことを扱っている間は、まだまだだよ、そんな小っちゃい話じゃないんだよ、と。
--それがこれからのあたらしい学問のはじまりなんだ--
出典:先哲が説く指導者の条件 『水雲問答』『熊沢蕃山語録』に学ぶ(安岡正篤・著、PHP文庫)