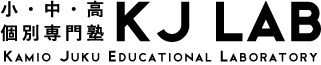「考える力」を養うのは、決して難問を解いたり偏差値を上げることだけではない。
偏差値が上がりやすいのは本人の努力はもちろんだが、その人固有の記憶力の多寡にも関係してくるので、偏差値が高いからといってその人の思考力が優れているというバロメーターにはならない。
偏差値の高い人は思考力が優れている場合が多いのは、あくまで傾向の話に過ぎない。
さて、この「考える力」というのは、社会で生活する上での日々の情報収集力にも関わってくる。考える力が弱いと自分が入手すべき情報も見逃し聞き逃し、何が自分にとって大切かが分からない前後不覚の生活を送ってしまう。
一方で「自分はどう考えるか」という思考癖をつけておくと、自分の体質・性格・気質に合った価値観を磨くことができ、自分の軸を太くして、更にその自分磨きに役立つ情報を日常生活から集めることができる。
自分の軸がなければ万事行き当たりばったりの行動になってしまい、自分にとっての無理や無駄も発生してしまう。
◆
当塾についての詳細な情報はこちらをご覧ください。