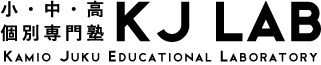たまたま書店で手に取った本だったが、
非常に勉強になったので、備忘録として気になった部分をメモしておく。
—
『発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ』
(小栗正幸・著、ぎょうせい)
■非行少年
非行少年と接していて痛感することは、彼らが「一人前のことのできる自分」を必死になって周囲に示そうとしていることだ。実際に、彼らの多くはすでに中学校二年生くらいから、「中学校を卒業したら高校には行かず、手に職を付けて働きたい」と考え始める。彼らのファンタジーの中では、飲酒、喫煙など、「大人と同じことができる」ことと、「一人前のことができる」ことが見事に融合している。
非行少年が一番元気になるのは、年齢で示すと13歳くらいから、18歳くらいの間である。そして、その背景には高校進学という進路選択の課題が絡んでいることをわかってほしい。
例えば、矯正施設で出会う非行少年には、中学卒業後高校に進学していないか、進学してもすぐに中退した子どもが圧倒的に多い。また、たとえ高校在学中であっても、高校生活はうまくいっていない場合がほとんどである。つまり彼らは、中学校に普通どおり登校し、高校にも通っている級友に対して、大なり小なり「挫折している自分」を意識せざるを得ない状態にあり、大人の真似事でもして突っ張っていないと、とてもやっていられないのである。
もっというなら、バイクの無免許運転を平気で行い、追いかけてくるパトカーを振り切ってしまうような、多くの級友にはできない「すごいことのできる自分」がいるということ。これが望ましくない方向で彼らを元気(活動的)にさせる原動力なのだ。
それでは、高校には進学せず、進学してもすぐに中退してしまった非行少年たちは何をしているのだろうか。意外に思われるかもしれないが、多くの非行少年たちは、パートタイマーやフリーターとして仕事をしているのである。もちろん、無計画な短期転職は当たり前に起こるし、職探しと称する徒遊期間もあるが、ともかく彼らは仕事を志向しており、そこには、「一人前のことのできる自分」というファンタジーの体現化がある。
とはいっても、現在の日本社会では、15歳から18歳までの間に、高校に行っていない子どもたちが仕事のできる職域は非常に限られている。それでも、彼らにはニートのような症例は驚くほど少ない。
高校卒業の段階では、普通に経過してきた子どもたちに比べ、彼らは経済的に優位に立っている。しかしながら、彼らの職業生活のスタートは、昇給もなければ、ボーナスもないような就労条件から開始されるのがほとんどである。仮にそうした状態から脱することができないと、30代になって、一度は追い抜いたように思えた多くの同級生たちとの間に、経済的ないしは社会的な逆転が起こす可能性が高まってしまう。
このころまでに、思春期のゆがみを修正できなかったかつての非行少年たちは、また「うまくいっていない自分」に直面させられることになりかねない。これが二度目の危機である。しかも、この30代という年齢は、子育てが本格化する時期でもある。さらに、かつての非行少年には、早く結婚して、早く子どもを作る傾向がある。
子育て年齢にある親が、かつて経験したような自己評価の低下にとらわれるとしたら、それが子育てに良い影響を与えるなどとは絶対に言えないはずだ。そうした状況が背景にあれば、子どもへの不適切な養育すら起こりかねないだろう。
要するに、最も深刻なことは、非行少年がまた非行少年を作ってしまうという、連鎖に陥る悲劇である。だから子どもは非行化させるべきではないというのが結論なのだ。
■二次障害としての非行化
平成17年から翌18年にかけて、少年鑑別所に入所した699名について、児童精神科医が軽度知的障害と診断した症例が19名(2.72%)、PDD(広汎性発達障害)と診断した症例が24名(3.43%)、ADHDと診断した症例が39名(5.58%)というものである。このうちPDD並びにADHDと診断された症例を合計すると、9.01%となる。また、ADHDと診断された症例39名のうち19名(48.72%)には、学習障害の合併が認められたという。やはり、少年鑑別所に入所してくる非行少年の10%から15%は、精密な発達査定を必要とする状態なのである。
■実態把握の遅れ
学校の教師などが子どもの発達的な制約に気づいても、保護者がそれを否定して結局支援の機会を逃してしまうもので、そうした子どもの一部が思春期に非行化することがある。
ただし、こうした保護者からの否認には、信頼関係が形成されていない状態での障害告知など、指導する側の対応のまずさが絡んでいる場合があるので充分注意するようにしたい。
要するに、相手が保護者であろうが、子どもであろうが、同僚であろうが、ネガティブな情報を伝えるときこそ、伝える側のコミュニケーション能力が試されるということだ。
■生活支援
趣味もなく、友達もいない。つまり生活が豊かでない子どもは、往々にして興味関心の持ち方が自己愛的(自己中心的)になりやすく、周囲を困らせることが多い。例えば、周囲を心配させるようなグロテスクなもの(死体とか人体解剖など)や、危ないもの(刃物とか火薬、あるいは毒薬など)、あるいは性的なもの(露骨な性描写や強姦、加虐的な性行為など)への偏執的な興味や関心が強すぎる子どもの多くは、ほぼ間違いなく生活面に豊かさがない。つまり、「趣味も友達もいない」という事実があるからだ。
その理由は、グロテスクなものや危険なもの、あるいは性的なものは、何らかの意味で万人の興味を引くもの、もっと言うなら、人間にとって「根源的な興味に火を付ける要素を含んだ刺激」になっているからである。
大切なことは、興味や関心のレパートリーが狭くなればなるほど、根源的ではあっても、社会に受け入れられないものへの関心が高まってしまうということだ。
ただ、この種の相談を受けて気づいたことは、例えば心配している保護者の側も、子どもと一緒に楽しめるような趣味を持っていない場合が多いということである。そこで、私がまず助言することは、「子どもに関心を持たせたいと思うことを、まず親が好きになる」というプロセスを設けてもらうことである。
好きになるといっても、必ずしも本気で好きになる必要はなく、子どもと一緒に少し楽しんでみる程度でよい。いずれにしても、家庭の中で子どもに対して趣味造りのファシリテーター役を演じられるのは親しかいないので、このプロセスは省略できないものになる。
要するに子どもというものは、良くも悪くも、親のしていることに関心を示すものなのである。
ただし、親があまりに真剣になってしまうと、子どもに強いストレスを強いる状況が形成されやすくなる。そうしてしまわないために、やっておくべきことがある。それは、子どもがどんな趣味に向いているのかのアセスメントを行うことである。要するに、子どもへの働きかけの科学的根拠(エビデンス)を満たすということで、少なくとも運動系の趣味に向く子か、理科系の趣味に向く子か、文化系の趣味に向く子かくらいは知っておく必要がある。
そこの次のプロセスに移る。子どもに適合する趣味の会のような団体の活動拠点に、まず親が子どもを連れて行くことである。ただ、勝手に親が決めるより、いろいろな同好会を示して子どもに選ばせるのも一つの方法である。
—(以上、抜粋要約)