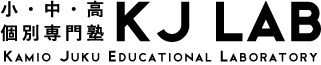昨年亡くなった落語家、立川談志が1965年に初めて書いた本「現代落語論」を読んでいる。真打に昇進し、柳家小ゑんから改名した直後の著作だ。この中で前座時代のエピソードが目に留まった。
~ある夜、麻布十番クラブが終演(ハネ)て一人で目黒行きの都電を待っていたがなかなか五番の電車はこない。150円の給金の中から家へ土産に買った鯛焼きをさっと吹いてきた風に吹き飛ばされ、それをひとつひとつ拾って泥をはたいているうちにたまらなく情けなくなってきて、落語家なんかヤメちまおうかとも思ったことがあった~
かの談志でもこんなことがあったのだ。
「現代落語論」は落語にまつわる様々を詳細に解説しており、技術書、哲学書のようでも論文のようでもある。そしてマニアックで、熱い。
七代目(自称五代目)立川談志が不動の大看板となったのは、やはり落語が好きで好きで仕方がなかったからだ。修行時代の大変な時期があったとしても、好きだからこそ苦労も乗り越えられるし、好きだからこそ機微もつかみもっと詳しくなれる。幼年から自分が「好き」だと思えることに彼は素直に従ったし、だからこそ落語というツボの中にどっぷりとハマって巨匠となった。むしろ落語と談志は不即不離、一体だったといえる。
何が言いたいのかというと、「ハマった」人生を送りたいと思うということだ。