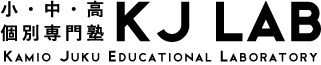昨年に引き続き『時代を見抜く力~渡部昇一的思考で現代を斬る』より、最終章「義務教育を廃止せよ」から抜粋。1975年の文章。
—(抜粋ここから)
教える方でも、塾の場合は教師側のイニシャティブと熱意と有能さと親切さが絶対に必要なわけで、デモシカ教師は存在する余地がない。勤務評定などは全く不要だ。評判のよい塾は必ずよいのであり、少しでも手を抜けばそういう塾は潰れるのだから世話はない。「教師にもストは許されるべきか」などという大問題も、私塾にとっては問題でない。教えたくない親の子供には教えなくてよいし、やりたくなければ塾を閉鎖すればよいのだ。
やる気のある先生しか塾はできないし、やる気のある生徒しかこない。先生は自分の信ずる方法でやれるし、厳しい指導をするところがあってよいし、合宿があってもよい。そういうやり方を信頼できなければ、子供を託さなければよいのだから。これこそ、あらゆる教育学の理想とする雰囲気であり、理想的教育の条件ではないか。それなのに教育を義務教役にして、組織を膨大なものにするから、教育それ自体から見れば二義的、三義的なことで大もめにもめているのである。
このような私塾は、必然的に小規模である。それがよいのだ。キリストだって弟子は十二人、孔子だって一度に教えた数はそれぐらいのものだったろう。吉田松陰また然り。こうした神の子、聖人、偉人でも、教える数はごく少ないのだから、普通の人間が教役組織の中で教えてそれほど効果が上るはずもないのである。勉強する場所は大きなビルディングである必要はさらさらないのだ。子供の精神はまだひ弱いので、建物や道具が立派すぎると、どうもしんみりと精神が開発されにくい。
こういう塾が沢山でき、同じ教育理念の人が数人集って、共同の塾を作るのも悪くはない。英語や数学や図画の先生が集ってやってもよいし、図画や工作や音楽の先生が集ってやってもよい。指揮の小澤征爾氏をはじめ、世界的な音楽家を雲の如く吐き出して世界を驚かした桐朋音楽大学も、最初は自分の校舎さえなく、生徒は先生のうちに通ったと聞いている。全くの塾である。高価な敷地に、高価な建物を建て、校長室や事務室を整備したりすればよりよい教育ができるという保証は全くないのである。
現在の日本の学校の問題の多くは、容れ物を整備したため、内容が落ちた、ということに帰着する。文部省も敷地や建物の”量”の監督はできるけれども、教育の”質”は監督できない。しかるに教育は質がすべてであるのだ。
◆
学校と塾が両方あって、児童が毎日、野蛮なほど長い拘束状態に置かれることから抜け出すため、学校の方をやめよ、と言えば、そこに出てくる反論は容易に想像できる。「塾に行くには金がかかるが、貧乏人はどうするか」というのが先ず第一にあるだろう。「父親の飲代と母親の美容院代を節約しろ」などということは言うまい。学校は当分、そのままにしておいてよいのである。ただ、塾に通ってそこで実力をつけている者がいたら、それを、学校に来なければならないという義務から免除してやればよいのである。
(中略)
この方式のもう一つの利点は、各個人が、マイ・ペースで進めることである。女子は平均して男子よりも早熟であるので、男女共学は困る、などということは全くなくなる。人間の個人の素質や、成長の速度はベラ棒に個人差が大きいのであるから、生れた時からの物理的年齢の数え方によるクラス編成というのは本当はナンセンスなのである。塾ならまったく自分自身の進度によるわけだ。頭の進んだ子や、体の発育のよい子は、少し早く高校に進学してもよいだろうし、その反対の子供はゆっくりやったらよい。しかしそれでも今まで通りの方がよい、という父兄の子供は今まで通りの学校にやればよい。
思い返せば、今年(1975年)の8月で「学制頒布」から数えて百三年になる。つまりざっと百年である。ここで一度、その使命を終えた巨大組織を静かに終焉させてみようではないか。日本の義務教役問題は、もはや絆創膏や小手術では何ともしようがないところまで行っているらしいのである。(P.346-350)
—(抜粋ここまで)
出典:『「時代」を見抜く力~渡部昇一的思考で現代を斬る』(渡部昇一・著、育鵬社)