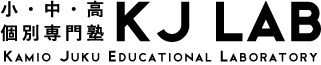塾で指導者の立場にいるということは、日々生徒からそれぞれの生き様を学んでいるということでもある。
上手くいく生徒・家庭、上手くいかない生徒・家庭、それぞれに固有のパターンがあるような気がしており、新しく入塾された生徒やご家庭と接しながらその断片をのぞきさえすれば、今後の先行きがどうなるかを何となく占えるようにもなってきた。
さて、学習塾の世界であろうが野球の世界であろうが、人間が生きていく道の哲学はどれも普遍的で共通しているように思う。料理でもスポーツでも、極めれば何のジャンルからでも人間は学び、向上することが出来るのだ。
2月に発売されたばかりのノムさんの新刊が書店に置いてあったので手に取ってみた。
私は常々、「人間は無視・賞賛・非難の段階で試される」と言い続けてきた。その人間が箸にも棒にもかからない状態であれば「無視」、少し見込みが出てきたら「賞賛」し、組織を担う中心的人物になったと認められる段階で「非難」する。
ここでいう非難とは、「その程度で満足していてはダメだ。もっと成長して本当の中心になってほしい」という期待が込められている。その真意を受け止め、悔しさを感じつつも、「どうにかして認めさせたい、見返したい」と思って精進を重ねることで、その人間は真の一流になることができるというわけだ。(P.30)
「褒めて伸ばす」という考え方があるが、これは時と場合によるもので、基本的に不要なことが多いと私は考えている。「褒めたら落ちる」という法則も一方には存在するからだ。
「この監督についていけば大丈夫だ」「この監督の言うとおりにやれば、勝てるに違いない」と選手に思わせることが大切であり、そのために人望や度量、風格、言葉、判断力、決断力、理論を身につけることが必要だ。そのためには、「オレは世界一に導くために、こういう野球がしたい」という監督の考えを選手に理解させ、動かすための意識づけをしていくことが肝心だ。(P.32)
指導者が上昇志向を持たないで、なぜ生徒を上昇させられるのか、と野村さんは喝破しておられる。
私が思うに、選手たちと積極的にコミュニケーションをとってばかりいると、選手たちから一目置かれるような存在として見られなくなるのではないかと考えている。その証拠に、渡辺が監督のときの選手は茶髪は当たり前、ユニフォームの着こなしだって裾が長く、まるでパジャマを着ているかのようだった。
外見の乱れは心の乱れにつながり、心の乱れはプレーの乱れとなって影響を及ぼしていく。実はこのことを理解していない指導者がほとんどではないだろうか。(P.74)
御意。
私も、塾内で生徒と不必要なまでにコミュニケーションを取るべきでないと考えている。先生と生徒は、一線を敷くべきだ。コミュニケーションは生徒が卒業してからで良い。
選手である以上、相手のチームと戦う前に、まずは監督と戦わなければならないのだ。つまり、監督にアピールして結果を残さなければ、試合出場のチャンスは巡ってこない。
私は後に監督になってから、「相手チームと戦う前に、まず監督であるオレと戦いなさい」と選手に言い続けてきた。試合で相手チームと戦う前に、監督に自分をアピールして、評価してもらわなければ試合に出る機会も与えられない。(P.92)
これも御意。
指導者の立場になると、生徒がこの課題をどのようなモチベーションで取り組んだのか、また解答を写しながらノート練習をした「フリ」をしているか、など全部筒抜けで見えてしまう。そういう生徒には当然指導側としてもモチベーションが下がるのは言うまでもない。結局、世の中は鏡の法則。作用・反作用の法則でできている。
たしかに努力は大事だし、努力しようとする姿勢は大切だ。だが、その方法を間違っていては、時間と体力を浪費するだけで、すべてが水の泡となってしまう。
私が日頃から「人間の最大の罪は鈍感であることだ」と言い続けているのは、このときの体験があるからだ。失敗を失敗として自覚していない者、失敗の原因を究明する力に欠けている者は、絶対に一流にはなり得ない。些細なことに気づいて変化し、その変化が大きな進歩を招く。一流と呼ばれる選手はみな、修正能力に優れている。同じ失敗は絶対にしない。二度、三度と繰り返す者は二流、三流。(P.100)
これ重要。
例えば単語を覚える練習で、「study study study study study…」と同じ単語を延々と横に繰り返して書いて「練習」と称している生徒を見ると、あくまで生徒にもよるが、「阿呆か?」とあえて辛らつに罵倒?することがある。
「何?字の練習をしているの?」と。覚えるためにどうすればよいか、ということを考えないでただ横に書いた単語を見ながら繰り返して書き続けているのは、正しい努力とは言えない。正しくない努力は誰も評価してくれないし、結果にも繋がらない。正しい努力とは何かを考えながら、目的本位になって練習方法を改善していくのが人間だ。それが出来なければ犬猫以下でしかない。
では、失敗を重ねないようにするためにはどうすればいいか。「なぜ、あんな配球をしたのだろうか」「どうしてあのボールが打てたんだろう」などと、感じる力を身につけることが大切なのだ。感じる力とはすなわち、その人間の持つ強い熱意、希望、夢だと思っている。そういう強烈な思いからしか、感じる力は湧いてこないものだし、この力を持つ人間は成長していくものだ。(P.100)
「鈍すれば貧す」だ。鈍感で気づきのない人間ではいけない。
鶴岡さんほどの監督ならば、人を褒めることへの基準点が高いだろうから、やすやすと選手を褒めることをしない。だが、そうした厳しい目で見てくれる監督の下で、若いときにプレーできたことは、私の野球人生にプラスとなった。
(中略)
無視されて三流、賞賛されて二流、非難されて一流。後に私が監督になった際、選手指導の基本となるこの言葉は、私が鶴岡さんに教えられた体験が根底となっている。非難されるレベルになれば、「うぬぼれるんじゃないぞ」「まだまだ成長の余地はあるんだぞ」という意味合いもある。鶴岡さんから教わったことの一つに「人を滅多に褒めないこと」。このことの意味を学んだことは大きかった。(P.103)
やたらに褒めまくるのは、私としては基本的に「気持ち悪い」。
監督が選手を飲みに連れていったり、食事に連れていったりするのは最悪だ。選手に対して監督としての威厳がなくなり、言葉の重みもなくなってしまう。監督は選手と勝負する部分がなければならない。野球の知識はもちろん、世間における常識、あらゆる雑学など、体力以外で選手に負けることがあってはならない。負けてしまえば監督としての権威が崩れ、それがチームの崩壊へとつながってしまう。(P.105)
一線を敷く、の話。
コラムニストで評論家の青木雨彦さんから、「評論とは、『よかったと言う人が5人、悪かったと言う人が5人』いればいいのですよ。よかったと言う人が5人いてくれたら、これで勝ちなんです」とアドバイスをいただいた。また師と仰ぐ草柳大蔵(だいぞう)さんからは、「一生懸命やっていれば、必ず誰かが見ていて評価してくれるものですよ」とも教えていただいた。(P.121)
これは究極のプロフェッショナル論ではなかろうか。「至誠」、どこにいても、誰に対しても一生懸命を尽くす。
西郷南州の、「人を相手にせず、天を相手にせよ」はまさにこのこと。
また、この時期に歴史書をはじめとして、政治、経済、国際情勢、科学、文学まで、ありとあらゆる本を読破した。とくに中国の古典の言葉には、「野球にも結びつくことが多い」と感心していた。そこで、「気に入った文章や言葉に響く文言を見つけたら、赤線を引いてノートに書き写す。こうしたことをベースに「野村の考え」を確立していった。(P.122)
読むだけではなくて、書写することの重要性。すると文が頭だけでなく身体にしみて入っていくのだ。これが生きた勉強。これこそが「アクティブ・ラーニング」だろう。
「世の中には、ものが見えない人が千人いれば、見える人も千人いる」後に草柳先生から教えられた言葉が、今でも脳裏によみがえる。見ている人はちゃんと見てくれているのだ。どんな仕事にせよ、信念を持って続けていれば、必ず陽が当たるときがやってくる。(P.123)
ブレるな!というノムさんの愛が伝わってくる。
「野球においてチーム力を向上させる一番のポイントは、監督の力量のレベルアップを図ることである。こう言うと、「チーム力をアップするには、ウィークポイントを改善して、選手を補強することなんじゃないですか?」と疑問に思う方もいるかもしれないが、実はそれは正解ではない。
監督が己に対して厳しく、常に知識や情報の収集に努め、成長しようという姿勢を見せていれば、選手たちもおのずと同じような姿勢になってくる。これはどんなに時代が移り変わろうと、絶対に廃れることのない、私の哲学と言い換えてもいい。(P.125)
指導者論再び。
指導者はその立場を利用して、自分の理論を部下に披瀝(ひれき)して「こうしたほうがいい」などとアドバイスをしたがるものだが、これは慎まなくてはならない。なぜなら、選手たちの「自ら考える力」を奪ってしまうからだ。
自分で考えさせるクセを身につけさせることで、自分で考えて行動できるようになってくる。考えて行動できない人間は、「答えを教えてくれるからいいや」と安易な考え方になって、伸びしろだって少なくなってしまう。(P.129)
教えるべき時に教え、教えるべきでない時に教えない。これが指導の要諦だろう。
これに対して鈍感な「なんちゃって指導者」が多い。指導の目的は、生徒が自身の頭で考え、自身の足で前進出来るようになることだ。自ずと、教えるべきタイミングとその教授量は最低限にしぼられてくる。
指導者に必須なことは感性。澄んだ感覚。生徒が発する「気と波動」を読み解くこと。これに尽きると私は考えている。
だが、今のプロ野球界を見ていると、コーチが選手に手取り足取り教えているケースが目立つ。「自分は指導者という立場なのだから、教えて当たり前」などと思ってはダメだ。相手の話をよく聞き、「なぜそうしたのか」「それはなぜか」「これからどうするのか」、そうした質問を選手に投げかけ、どんな答えが返ってくるのか、その反応を見ることが大事だ。ときには選手から思いもよらない答えが返ってきて、指導者が新しい視点や事柄を知ることだってあるだろうが、指導者が答えまで言ってはいけない。
さらに言えば、選手が指導者の質問から答えを発することで、その発言自体に選手が責任を持つようになる。有言実行という言葉があるように、人は自分で言ったことに対して責任を感じるようになるものだ。(P.131)
そう。生徒自身にどうすべきか、答えを言わせることなのだ。
そうなるために最大限の環境と道筋を周到に用意するのが指導者の仕事。答えだけホイホイ教える程度の仕事なら、先生など要らない。スタディサプリで充分。
つまり大切なのは、「動くと見せかけて、相手を混乱させること」なのである。(P.141)
また数学か、と生徒に思わせる前に「え!ここで社会?」と意表をつく授業構成にすることも、指導テクニックのひとつだ。杓子定規なものは何一つない。それこそ生徒の「気と波動」と読みながら、同時に達成目標も頭に描いて、それでいて生徒が常に新鮮な気持ちで授業に向かえるようにすること。
新しく入塾した生徒が「80分があっという間だった!」と感じてしまうのは、そういう工夫が土台にあるからだ。
「この選手を一人前にしたい」という思いは、どこのチームの監督やコーチにもあるはずだ。そのためには嫌われることも厭(いと)わないという姿勢こそが、本当の愛情であると、私は考えている。そうすれば厳しい練習を課すことだってできるし、じっくりと観察するようにだってなる。おのずとどのタイミングでどんな言葉をかけたらいいか、あるいはかけてはいけないのかだってわかるようになるものだ。(P.142)
指導者は時に、嫌われ者にも、憎まれ者にも、敵にもならないといけない。善悪二元論で言うなら、「悪」が存在するから「善」が見えてくるのだ。指導者は時に「悪」になって生徒の「善」を引き出させる役回りから逃れることは出来ない。
選手の才能を開花させるのは、指導者の務めであるのは間違いないが、普段は厳しく接し、タイミングをみて褒めることで、選手はその言葉の重みを感じ取り、発奮するものだ。そのことを鶴岡さんから教えられ、そして岩隈に実践したのである。(P.145)
褒める行為が最も効果的にスパッと生徒に入るタイミングを見込んで、褒めること。それでこそ効果がある。いつでもどこでも褒める大人では、生徒も見抜く。なんとなく生ぬるさを感じてしまうものだ。
つまり、本人が何か言ってほしいというときにすかさず褒めるからこそ、褒める行為が大きな力をもたらすのだが、必要ないときに褒めても、大して意味がないばかりか、マイナスに働くことだって十分にある。(P.149)
すこぶる御意。このマイナスに働くということの一つが、先述の「褒めたら落ちるの法則」。
巨人監督時代の川上さんは野球の話はほとんどせず、人としていかに生きるべきか、あるいは人の和の大切さ、礼儀やマナーといった人間学を中心に話していたそうだ。野球人である前に、一人の人間としてあるべき姿を説き、ONすら特別扱いは一切せず、叱るときは徹底的に叱った。(P.155)
「人間の土台」をつくることが大切なのは、学習塾も野球も、どこも同じらしい。
今のプロ野球選手のほとんどは、家庭や学校で常識やしつけ、マナーなどを教えられていないと考えた方がよい。現代の若者はすべて親や指導者、すなわち大人が作っているということを、忘れてはならない。(P.164)
御意の連続。
ということで、出典は「名将の条件~監督受難時代に必要な資質」 野村克也・著(SB新書)。