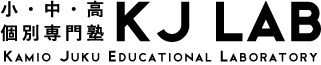2022年度の五ツ木模試を受験した中学3年生の実人数を見てみよう。
第1回(5/15)3,816人
第2回(6/12)4,890人
第3回(7/10)7,273人
第4回(9/11)27,424人
第5回(10/9)26,201人
第6回(11/13)47,416人
第7回(12/11)17,720人 ※特別回
第8回(1/22)5,317人
首都圏最大手の模試業者、進学研究会(大阪進研の関連会社)の会場模試「Vもぎ」では6月から1月まで計11回、すべて自由に会場を選択できる。
ところが大阪の五ツ木模試では、計8回のうち7回を所属する中学校ごとに受験会場が強制的に割り当てられる。会場を自由に選べるのは12月の第7回(=特別回)のみだ。
また、大阪進研の「Vもし」では計9回のうち会場模試は3回だけで、残り6回は塾内模試になっている。
なぜ五ツ木模試は自由に会場を選べないのか?なぜ大阪進研は会場模試が少ないのか?
受験者数の推移を見て、その理由が納得できた。
2022年度、大阪府下の学校に在籍した中学3年生は74,056人(令和4年度・大阪府学校基本調査)。これは国立・公立・私立すべての学校を含んでいる。また、五ツ木模試は京都や奈良など関西の他府県でも開催されるため、受験者数に他府県の受験生を多少含んでいる。更に、オリジナルの模試を実施する大手進学塾に通う生徒は五ツ木模試を受験しない。
以上の前提があるが、それでも単純に第6回で「74,056人中の47,416人」が五ツ木模試を受験したとなれば、まあまあ高い受験率と言えるだろう。11月は最も精度の高い模試が実現できていると言える。
ところが、5月から7月の受験者数が圧倒的に少ない。この少なさで受験生に会場を自由に選ばせてしまえば会場確保の見通しが立たず、模試業者としては大赤字を垂れ流すことになる。つまり、五ツ木模試にとっては勉強熱心な中学校、そうでない中学校によって模試の受験者数が見通せるから、受験会場を中学校ごとに割り当てた方が会場確保において合理的なのだ。
9月以降の五ツ木模試は私立高校の入試相談の材料となるため、受験者数が一気に増える。それでも11月に比べれば半分程度。そして11月になって、「仕方ないから受けておくか」という層が参入してきて受験者数が一気に跳ね上がる。しかし、12月になれば私立専願が中学校の懇談でまとまり始めるので、大幅に受験者が減る。
そんな状況で開催される12月の特別回で会場選択を受験生に任せているのは、五ツ木模試としては太っ腹としか言いようがない。更に言えば、12月から1月にかけての五ツ木模試は真剣に高校入試を受けようと準備している層が残っている。
大阪進研の「Vもし」も同様で、特に1学期は会場模試を実施したくても動員が見込めない事情があるように思う。これらはやはり、勉強面には総じて熱心でない大阪独特の風土によるものと言えるのかもしれない。