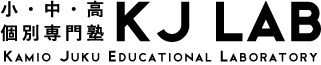細胞生物学者、歌人でもある京都大学名誉教授の永田和宏先生の著書より。全国の高校入試で国語長文問題の課題文として近年用いられることの多い『知の体力』。
必要な知識というものは、現場で必要になったときに、調べて仕入れるのがもっとも身につくもので、ただ漫然と机に向かって講義を聞いているだけでは、実践の場におけるほんとうに必要な知識は自分のものにならない。(P.87)
順序立てて体系的にまとめられた授業は合理的だけれども、それが100%そのまま生徒の身についているとは限らない。授業を受けているから成績が上がるわけではない、というのはそういうことで、不器用ながらも自分で手探りで参考書や辞書、インターネット等で調べたことの方が自分の身につきやすいのは、そこに「当事者性」が発生するから。
「ウンチの固形成分の三分の一は、みんなが答えたように、食べ物の残りかすです。ではあとの三分の二は、なんだと思う?」
「その三分の一は、小腸などの粘膜細胞の死んだもの。前に、小腸の一番外側を覆っている上皮細胞、粘膜細胞の寿命は2~3日だって言ったよね。短時間働くだけ働いて、すぐに死んでしまう上皮細胞の死骸なんです。そして最後の三分の一が、じつは皆さんの腸のなかにいるバクテリアの死骸なんです」と繋がっていくのである。(P.106)
上記は「能動的学習」の講義のひとコマ。
1957年に京都大学教養部の助教授になった森毅先生は、それから14年後、教授昇任の審査を受けることになった。そのとき問題になったのが、助教授就任後の数学者としての業績が、たった2報の論文しかなかったことであったという。
「これほど業績がない人物を教授にしてよいのか」と問題になったが、「こういう人物がひとりくらい教授であっても良いじゃないか」ということで京都大学の教授となったとのエピソードが伝わっている。本当かどうか、私にはわからないが、いかにも京大らしいエピソードで私は好きである。「こういう人物がひとりくらい教授であっても良いじゃないか」という部分、その緩さが大切なのである。(P.116)
森毅(もり・つよし)先生。懐かしい。
授業料を払って授業を受けているのだから、授業は一種の商品である。しかし、いっぽうで授業は、受けたいと思っていることが、その基本にあるべきなのではないか。欲しくもない顧客に、商品を売りつけるといった商売と、それはどこか本質的な違いがあるはずである。
大学における教育も、授業料に対する対価としての講義、授業という考え方はどこかで捨てたほうがいいと思っている。同時に、学生を金を払っているお客さまと考える考え方も受け容れがたい。
授業は、そしてそこで提供される「知」は、受け取って当然という態度からは、ほんとうに大切なものが欠落してしまうと思うのである。教師の側も給料をもらっているから、とりあえず授業をするということでないことは当然のことであるが、受け取る側も、与えられて当然、それは権利であるといった考え方がはびこると、大学における「知」の伝達が深刻な困難に直面することになる。(P.119)
大学だけでなく学習塾も全く同じで、「塾における各種サービスは商品である」と無意識のうちから思い込んでいる人々(物質主義者)も現代には一定の割合で存在するわけで、そういった人々ほど「塾の効果(指導効果、通塾効果)」を得られていない(当塾においてはだんだんと居心地が悪くなる)ことは当塾の過去の事例からもよくわかる。
先生から「知」の一部をわけていただく、そのためには先生の言葉の端々に述べられずあるものまでなんとか吸収したい、そんな姿勢こそが、本来の意味での「教授」ということなのではないだろうか。教える側と、それを受け取る側の両方あっての教授と言う行為なのである。受け取る側が、もらって当然といった態度からは、何も伝わらないと思われてならない。(P.120)
御意。
私は大学という場を、自らが得てきた「知」の集積を、もう少し希望的に言えば「知の体系」を、個々の場合に応じて、個々の状況に対応して、いかに組み替えて、その場に固有の「知」として再構成できるか、それをみずからの手で行えるように訓練する期間だと考えている。それが「知の体力」ということである。
それは教師や、まして親から教えられるものではなく、自らが考えて最善手を模索するというところに意味があるのである。最善手を得られるかどうかが重要ではなく、それを自分で模索するというところに意味があるのだ。(P.144)
本書のタイトルにもなっている山場の部分。
先週の卒塾感想にもつながる話。手先と頭脳を動かしながら、<自分で気づかなければ>成長が得られず、前進することもできないのだ。
多くは失敗するだろう。何しろ模範解答などはなく、正解もあるのかどうかわからない。誰かに聞いて教えてもらえるものではない問題にチャレンジするのが大学における教育である、あるべきである、と考えている。その数限りなく繰り返される失敗のなかにこそ、将来、自らの力で「知」を有効利用できる戦略が隠されているのである。
子がそのような「果敢な失敗」に挑むべき時に、親や教師が救いの手を差し伸べることの弊害は改めて言うまでもないだろう。それはその場を救うことにはなっても、結局は、子の自立を妨げる以外のものではないのである。失敗の芽をあらかじめ摘んでしまうことは、成功への道を閉ざす以外のなにものでもない。失敗体験こそが、次に同様の問題に直面したときに成功へと導く必須の布石なのである。失敗を多く経験してきた人間こそ、いざというときに肝も据わり、冷静な判断を行うことができる。
いつも手を差し伸べてなされる成功体験は、成功体験でもなにものでもなく、逆に困ったときは、誰かが助けてくれるという安易な依存体質を形成させるだけのことであって、益するところはなにもないと私は思っている。(P.145)
ジャンルを超えて、これは普遍的な話である。
さて、
「細胞生物学者」と「歌人」。一見、全く異なる分野に思えるが、著者にとって細胞生物学は歌であり、歌は細胞生物学でもある。つまり、その境界線というものに意味はない。
平然と振る舞うほかはあらざるをその平然をひとは悲しむ
君と同じレベルで嘆くことだけはすまいと来たがそを悲しむか
君よりもわれに不安の深きこと言うべくもなく二年を超えぬ
永田和宏 歌集『後の日々』
今ならばまつすぐに言ふ夫ならば庇って欲しかった医学書閉ぢて
文献に癌細胞を読み続け私の癌には触れざり君は
河野裕子 歌集『庭』
2010年に64歳で亡くなった、永田先生の夫人であり歌人の河野裕子(かわの ゆうこ)さん。
晩年は乳がんを闘病しながらも、多くの歌を詠んだ。その中での夫と妻がそれぞれ詠んだ、短歌。
夫は乳がんの最新治療法を求めて文献を読んだり専門家を訪ねたりしながらも、病気に負けてなるものか、と強気に過ごす。
妻が求めていたものは、医学的な知識でも励ましでもなく、ただ寄り添い、一緒に悲しんでくれる存在。
そんな二人の心の対比に胸が締めつけられるものがあった。
※出典『知の体力』(永田和宏・著、新潮新書)