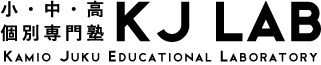昨日は神社の勉強会で聖徳太子の「十七条憲法」を扱った。
出所はWikipediaだが、要約・意訳しながら読んでみたら、これがなかなか面白い。暗記モノとして「十七条憲法」を読むとつまらないが、自分の生活と隣り合わせにあるものとして読むと、1400年前の読み物とは思えないくらいに身近に感じる。
—(ここから)
▼十七条憲法(じゅうしちじょうのけんぽう)
604年(推古天皇12年)に聖徳太子が制定した、日本最初の成文法。官僚や貴族に対する道徳的な規範が示され、儒教や仏教の要素をおりまぜている。
【1】お互いの心が和らぎ協力することが貴い。ところが人には党派心があり、大局を見通している者は少ないから争いを起こすようになる。しかし、人々が和らいで睦まじく話し合いができるならば、事柄は道理にかなって何事も成し遂げられる。
【6】悪を懲らして善を勧めることは良いしきたりであるから、他人のなした善は隠さずに表に出し、他人が悪をなしたのを見ればそれを止め、正しくしてやりなさい。
【7】賢明な人格者が官にある時には誉める声が起こり、邪(よこしま)な者が官にある時には災禍や乱れがしばしば起こる。世の中には生まれながらに聡明な者は少ない。よく道理に心がけるならば、聖者のようになる。
【9】何事を為すにあたっても、真心をもってすべきである。善いことも悪いことも、成功するのも失敗するのも、この真心があるかどうかにかかっている。
【10】他人が自分に逆らっても激怒しないように。人にはそれぞれ思う所があり、それぞれ自分が正しいと考えている。他人が正しいと考えることを自分は間違っていると考え、自分が正しいと考えることを他人は間違っていると考える。しかし、自分が必ずしも聖者なのではなく、他人が必ずしも愚者なのでもない。両方ともに凡夫にすぎないのである。正しいとか、間違っているとどうして定められようか。
【17】重大な事柄は一人で決定してはならない。必ず多くの人々と共に論議すべきである。多くの人々と共に論じて是非をわきまえるならば道理にかなうようになる。
—(ここまで)
私の印象に残ったのは【10】番。「人にはそれぞれ思う所があり、それぞれに自分が正しいと考えている」・・・そう、だから人と人は衝突するのだ。「両方ともに凡夫にすぎないのである」・・・つまり謙虚でいなさい、と。お互いが驕らず謙虚であれば、それこそ聖徳太子の「和を以て貴しとなす」が実現できるのだ。
◆
当塾についての詳細な情報はこちらをご覧ください。