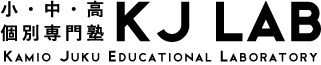中学生の頃、修学旅行で京都の清水焼を体験する機会があった。素焼きの器に文字を書いて、後日職人さんが本焼きをして東京まで送ってくれるというものだった。
「道はある」と私は書いた。
困難な壁にぶつかっても、乗り越える道もあれば、穴を開けて通り抜ける道もある。壁沿いに歩く道もあるし、引き返す道もある。道は必ず存在する!ということを、今思えば老けた考えだが、当時は真剣に思っていた。
「死ぬ時は手ぶら」というのも、当時つけていた一行日記に書いていた言葉である。
人は死ぬ時、誰一人として物を持ったまま死ぬことが出来ない。手ぶらのままで死んでいくのだから、経験と記憶を積み上げて、豊かな心に成熟させることの方が大事なのではないか、と当時なんとなく考えていたようだ。
今でも私は身の回りの物が増えることを好まず、不要な物を捨てることに精を出してしまう。神尾塾の教室内にも模試の案内などのポスターを貼ることは嫌いだし、書棚の本も、長らく使わないものはどんどん捨てている。その代わりに質の良いもの、有意義なものばかりが残っている。物を捨てるということは、物を粗末にすることではなく、使えるもの、大切なものを明確にするという究極の「物を大切にする」行為だと私は考えている。
日本の伝統建築が木造で出来ているのは、日本が自然災害に見舞われやすい国で、「形あるものはいずれ壊れる」ことを前提にしているからだと言える。木材ならば石や鉄鋼に比べて再生産がしやすい。伊勢神宮の20年おきに建て替える式年遷宮は、物を保存することに価値を置いているのではなく、20年おきに同じものを作るという「作る精神」の伝承に重きを置いていることに注目しておきたい。
さて、地球上で地震や火山の噴火が起きるのは、地球が生きている証拠である。地盤が動くのも形が変わるのも、岡本太郎ならば「地球は生きている!」と歓喜することだろう。その生きている地球の上にアスファルトを敷いたり橋を架けたりして、地球の表面を固定化させ、それらがいざ壊れた時に嘆き悲しんでいるのは人間だけである。地球という生命の方がよほど先を進み、つい思考が固定しがちな人間の方がよほど遅れているのかもしれない。