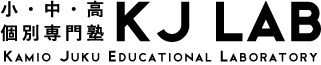北欧のフィンランドで2025年8月から小・中学校でのスマートフォンの使用を制限する法律が施行される。記事を見てみよう。
「小中学校の生徒によるスマートフォンの使用を制限する法律がフィンランドで成立」
Gigazine(2025年5月1日)
フィンランド議会が、小学校の児童や中学校の生徒によるスマートフォンなどモバイル端末の使用を制限する法律を承認しました。法律は夏休み後、2025年8月から施行されることになっています。
この法律は、小中学生によるスマートフォンの使用を全面的に禁止するものではなく、一定の条件下で使用を禁止するもの。一例として、授業中にスマートフォンを使うことは禁止となります。
電話したり、勉強のサポートに使ったり、健康関連の問題に対処したりする際の使用にあたっては、教師から特別な許可を得る必要があるとのこと。
なお、当該端末によって学校で混乱を招くような事態が引き起こされた場合、教師が没収する権限も付与されています。
すでにデンマークでは2025年初頭から、すべての学校で携帯電話の使用が禁止されています。デンマーク福祉委員会によると、多くのデジタルプラットフォームでは利用できる最低年齢を定めていますが、実態として、国内の子どもの94%は13歳になる前からアカウントを持っており、9歳から14歳の子どもが1日にTikTokとYouTubeで平均3時間を費やしているとのこと。福祉委員会のラスムス・マイヤー委員長はニュースサイト・The Guardianに対し「学校がデジタルプラットフォームに植民地化されるのを防ぐために対策が必要です」と述べ、ヨーロッパの他の国々にも対策を呼びかけたとのこと。
このほか、ノルウェーでも政府が「テック企業は小さな子どもたちの頭脳にとって敵」と表現し、SNSを利用する最低年齢を15歳と厳格化しています。また、フランスも2018年に小中学生の校内での携帯電話使用を禁止し、15歳までの子どもを対象に携帯電話を使わない日を作る「デジタル小休止」が試行されています。
※記事はこちらから転載しました。
近頃入塾された生徒がバッグの中を覗き込んでゴソゴソとしていたため、何事かと思って私も覗き込んでみたらスマートフォンの画面に「AIチャットくん」なるアプリが見えてきた。
LINEのトーク機能を利用してChatGPTが質問に答えてくれるようだ。
どうやら、その生徒は国語の問題で対義語を調べようとしていたらしい。
しかし、仮に「AIチャットくん」に答えを教えてもらって、答案用紙に書き写して、そこに何の意味があるのだろうか。ここには「考える」行為が一切伴わない。
「考える」ことなしに答えを埋めるだけの行為ならば、わざわざ塾に来ること自体に意味がない。
デジタルデバイスの普及により「考える」人と「考えない」人の差が更に広がる。「考えない」側の人を「考える」側にいかに引き寄せるか、それが今日における塾の役割の一つとなっている。