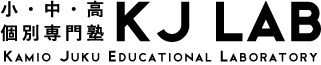中国料理・脇屋友詞シェフの自伝。
北海道での幼少期から、東京で始めた修業生活。先が見えず延々と続く鍋洗いの時代、そしてホテルの料理長就任から自身の店の立ち上げまで。
そこで何を考え、どのように行動してきたのか。仕事とは何か、仕事に向き合うとはどういうことなのか。
社会人が読むなら、自分の仕事と重ね合わせながら。学生が読めば、自分の進路をどのように切り開いていくか。
地道で、緻密で、猛烈な一所懸命を続けた脇屋シェフの姿勢がズシンと胸の中に響くだろう。
少なくとも、僕は違った。
ずっと死力を尽くしてきた。
不平たらたらで、いつも目の片隅で辞めるチャンスを探していた十五の春でさえ。
迷ったり、悩んだり、信じられなくなったりすることはある。
けれど、目の前の鍋だけは必死で磨いた。
その先に、道が続いていた。
目の前の仕事が、自分の仕事だと思えるかどうか。
この道をずっと歩いてきて思うのは、結局のところそれだけだった。
何かをなせるか、なせないかの差は。
才能の差でも、運の差でもない。
かなえたい夢がなくても、焦ることはない。
今自分の目の前にあることに、とりあえず必死で取り組んでみることだ。
それが心底自分のなすべき仕事だとわかったとき、人生は必ず変わる。
僕はそれを知っている。
『厨房の哲学者』(脇屋友詞・著、幻冬舎)P.166-167より抜粋