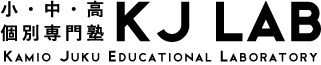一昨日、卒業生のH・K君と食事をした。
H・K君は現在とある市役所の児童相談の部署に勤務している。2年前に社会福祉士を取得したため、その資格を生かして児童虐待を中心とした行政対応と当事者へのカウンセリングおよび相談を行っている。
食事やスタバでのお茶も含めて5時間くらい話し込んでしまった。その中で私が関心を持ったことのひとつにH・K君の勉強法がある。そのことを書いてみたい。
当塾に5年半在籍したH・K君は「書き取り」を伴う勉強が苦手で、その意味で「書き取り」を中心とした従来型の中間・期末テストで最も苦労したタイプだ。
その彼が転機になったのは、コロナ騒動の発生した大学3年だと言う。大学の授業がオンラインに移行して、録画を何度も見返せる授業システムになった時に、自分は書いて練習したり書いて覚えるよりも、動画を繰り返し視聴して音声でインプットした方が自分の頭に残ることを理解したのだ。
そして、テストも筆記ではなくマークシート形式を選んだ方が枠を塗り潰すだけなので自身のストレスも少なく、「書き取り」に足を引っ張られることなく自分の力を発揮できる。H・K君にとって勉強は「書き取り3割、音声7割」という。
これを聞いてなるほどと私が思ったのが、学校で書き取り型の勉強やテストで上手くいかない生徒が、英検で上位の資格を取りやすいということを。英検は1次がマークシートで2次が音声なので、書き取りの苦手な人でも取り組みやすい。
実際、H・K君が受験した社会福祉士はマークシート形式で、合格率が約5割の難関資格だが準備し尽くしたH・K君にとっての障壁は少なかった。
彼が言うには「書き取りが苦手な子に書き取りを強要するのは拷問でしかなく、自分に合った勉強法を考えることが最も大事」と。H・K君は現在、スキルアップのために精神保健福祉士の取得を目指している。そのために仕事を続けながら大学にも再入学する。彼は再び、自分に合った勉強法で進めていくことだろう。
私にとっても学びと収穫の多い5時間であった。